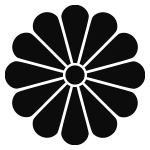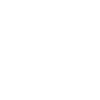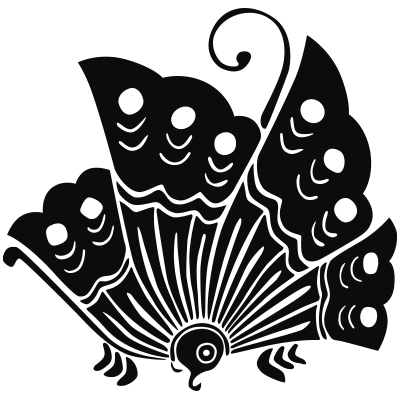家京平松
三条家
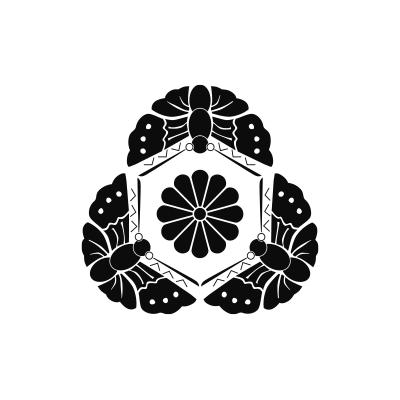
家 紋 三条蝶
替 紋 十二葉菊
本 姓 松平京家鹿苑寺流嫡流
始 祖 三条正永(松平信綱)
家 祖 三条輝綱(松平輝綱)
中 興 三条亨輝(皇霞京)
別 称 松田宗家
通 字 亨
流 派 冥神流
家 業 ブランド事業
根拠地 京都府 東京都
菩提寺 岡寺
分 家 広幡 七条 町尻 山井 大河内 園池 桜井 梅渓
東久世 伏原 澤 勘解由小路 外山 長沢 清水谷
植松 清岡 鷹司 高津 三室戸 北小路 藤井 壬生
慈光寺 土佐 新井 久留島 本居 石川 平田 生田
矢野 箕作 福澤 上野 吉野 松田 伊藤 谷口 二宮
千葉 中沢 根岸 楠本 陸奥 江木 朝吹 芥川 前田
高村 林 柳原 龝吉 沢村 並木 高峰 織田 川上
鶴見 池 平賀 狩野 司馬 笠森 蔦屋 柳屋 葛飾
只野 戸田 嵯峨 野中 中村 松下 佐山 大石 松岡
英 今井 松永 黒沢 鶴賀 麻田 中川 長久保
河合 高橋 猪飼 橋本 岡 木戸 松本 岡村 木村
黒駒 浅利 北里 三橋 西野 伊藤 山葉 御木本
長野 夏目 野口 布施 森 樋口 二葉亭 幸徳 九条
秋山 岸田 谷崎 中田 塚本 升田
婚姻家 井上 板倉 大川 古川 鈴木 朝倉 明石 堀田 酒井
戸田 後藤 肥田他
松田頼通の次男正永を祖とする。
代々、左大臣や太政大臣を歴任し、祖松田家で初の太政大臣兼左大臣となった官職を極官とし、天皇の補佐する。
明治維新では内務省を創設し、内務卿として実質的・事実上の初の内閣総理大臣や内閣総理大臣を二代に渡り務める。
令和に至り、ブランド事業で三条家の再起をはかる。
ゆき
亨
象形文字で先祖神を祀った場所から「たてまつる」、
「神意にかなって物事がうまく通る」意味から物事が支障なく行われる道理に適う思慮に富んだ冷静に判断する聡明な姿勢。
3 - 7 - 7 - 15
三条亨輝
字画の陰陽配列は全て奇数になり陽だけで構成された配列である。鹿苑寺流の陰にあたる系統にて、信輝流から正路流まで三家ずつ4回、正敬流は六家、輝聴と輝照は七家が2回続く。
「輝」の元の通字に着目し、輝聴流七家、輝照流七家で、条は七画であるからその後に来る画数は七画の漢字が入る。輝照と関連された内容から七画である「亨」が妥当な漢字と見当が立ち、陰の反対である陽の配列で構成された名前が導き出される。つまり、陰は終わり陽に輝く。亨輝に対し霞京の「きょう」の位置が上下逆になる形も祖が意図した証と捉える。
「至」以外の「ゆき」と読む漢字で、自身が良いと選んだ漢字も「亨」であり、利害が一致し非の打ち所はない。寧ろ、「亨」の方が美しい。誕辰和色の濃紫色の別名至極色から「彩」の姓名判断を行えばその結果に誰もが理解を得る。
松平京家、亨輝、霞京と三つ並び、判断結果は±ゼロで奇妙な結果である。
三条輝聴
輝聴は福澤諭吉である関連性を示すものは、お金の札である。福沢諭吉の前の一万円札は聖徳太子。
聖徳太子は一度に十人の話を聞き分けられたという逸話や聖徳太子が推古天皇に対し制定した冠位十二階の最高位である大徳の濃紫色から三条亨輝と福澤諭吉を紐付け、聖徳太子は大宝令以前の太政大臣の役割として推古天皇の元、共同統治者・政務代行者として治世し、三条輝聴は日本の最高位太政大臣である内容を示すと共に、三条輝聴は福澤諭吉である事実関係を示す。
輝聴は亨輝から数えて7親等にあたる点においても、姓名判断や誕辰和色の占いを通じて亨輝の名に関連性を持たせているのがわかる。
「うる」の反対は「うらない」。つまり、「読売」の反対は「占い」。亨輝の「亨」の熟語に「亨人(ほうじん)」という言葉があり、皇の姓の皇室の名から「亨人」が導き出され、料理人を意味する。関連性から亨人は「巨人」で、輝耡流の宮内省の料理人である秋山徳蔵と紐付けられ、徳太郎は吉野作造、三条輝照、山科家と関係性を示す。
桓武天皇 ─ 略 ─ 平業房 ─ 山科教成 ─ 略 ─ 教定
┌──────────────────────────────────────┘
│
└ 松田頼盛 ─ 頼直 ─ 頼貞 ─ 頼近 ─ 頼源 ─ 頼仲
┌──────────────────────────────────────┘
│
└─── 善通 ─ 頼済 ─ 信頼 ─ 家頼 ─ 頼信 ─ 達頼
┌──────────────────────────────────────┘
│
└─── 頼勝 ─ 頼通
┌────────────┘
│松平三条家始祖
└ 三条正永 ─ 輝綱 ─ 信輝 ─ 信祝 ─ 正温 ─ 正升
┌──────────────────────────────────────┘
│
└─── 正路 ─ 正敬 ─ 輝聴 ─ 輝照 ─ 輝耡 ─ 輝成
┌──────────────────────────────────────┘
│
└─── 輝治 ─ 輝政
┌────────────┘
│松平三条家中興の祖
└─── 亨輝
三条家第十五代当主
三条亨輝 [哲学者]
人並外れた洞察力を持つ。
日本の新たな誇りの基礎を作る、三条ブランドの構想。
独自の流儀、「冥神流」の構想。
松田宗家第二十九代当主/さんじょうゆきてる
1848-1882
三条家第十二代当主
三条輝照 [公家 華族 政治家]
《正一位太政大臣兼左大臣大勲位公爵》
政治の革命児。
近代の基礎を作り、国会制度を制定させた。
松田宗家第二十四代当主/さんじょうてるあき
1596-1662
三条家第一代当主
三条正永 [公家 清華家]
《正一位太政大臣兼左大臣》
政治の天才。
江戸幕府の基礎を作り、平和な世の安定をもたらした。
松田宗家第十五代当主/さんじょうまさなが
松田頼信 ─ 松田頼通
╟──── 松田信実(三条正永)
織田信長 ─ 織田愛子
安場一平 ┈ 安場保和 ─ 安場和子
╟──── 後藤愛子
後藤實喜 ┈ 後藤實崇 ─ 後藤新平
戸田氏正 ─ 戸田氏共 ╟──── 三条輝治
╟──────┐
岩倉具視 ─ 岩倉極子 戸田米子
╟──── 三条輝成
酒井忠発 ─ 酒井万 三条輝耡
松平京家頼信流
堀田万 ╟──────┘
╟─── 三条輝照
松平京家鹿苑寺流
三条輝聴
小島里(内妻)
╟──── 朝比奈隆
宇治橋嘉一
╟──── 渡邊くに
渡邊よし
╟───── 肥田 某 ─ 肥田 某
松平西家光秀流
肥田為良 ─ 肥田籌一郎 ╟─── 三条亨輝
松平京家鹿苑寺流
三条輝耡 ─ 三条輝成 ─ 三条輝治 ─ 三条輝政
女系特記人物
1908-2001
松平西家盛秀流
朝比奈隆 [指揮者]
《従三位勲三等旭日中綬章》
大阪フィルハーモニー交響楽団(大阪フィル)の音楽総監督を務めた日本の指揮者。
あさひなたかし
1858-1936
松平京家信頼流
戸田極子 [華族]夫 戸田氏共
《鹿鳴館の華》
優雅な物腰と美貌から陸奥亮子と共に「鹿鳴館の華」といわれた。
とだきわこ
1858-1936
松平西家流
渡邊嘉一 [土木技術者 実業家]
《工学博士》
日本土木史の父と呼ばれる。旧姓、宇治橋。1877年に上京し、工部大学校(東京大学工学部)予科を経て、同校土木科に官費入学。在学中、二十四歳の時、大鳥圭介に才能を買われ、1882年、大鳥の仲介により海軍機関総督横須賀造船所長渡邊忻三の長女の婿養子となる。
わたなべかいち
1857-1929
松平京家頼信流
後藤新平 [医師 官僚・政治家]
《正二位勲一等伯爵》
愛知医学校長兼病院長。台湾総督府民政長官。南満洲鉄道(満鉄)初代総裁。逓信大臣、内務大臣、外務大臣。東京市第七代市長、ボーイスカウト日本連盟初代総長。東京放送局(日本放送協会)初代総裁。拓殖大学第三代学長を歴任した。
ごとうしんぺい
1854-1936
松平京家信頼流
戸田氏共 [華族 外交官 宮内省官僚]妻 極子
《従一位勲一等伯爵》
大垣戸田家の十二代目の当主で、美濃国大垣藩第十一代(最後)藩主、同藩初代(最後)藩知事。オーストリア=ハンガリー全権公使、式部長官などを歴任した。
とだうじたか
1835-1899
松平京家頼信流
安場保和 [官僚 政治家]
《従三位勲二等男爵》
江戸時代には肥後国熊本藩士であり、横井小楠の門下生だった。戊辰戦争で官軍に従軍して戦功を挙げた後、明治政府の高官として活躍し、福島県令、愛知県令、元老院議官、参事院議官、福岡県知事、愛知県知事、北海道庁長官などを歴任した。
やすばやすかず
1830-1889
松平西家光秀流
肥田為良 [幕臣 技術者 官僚]
《日本の造船の父》
伊豆国賀茂郡八幡野村の生れ。
通称は浜五郎、春安五男、長崎海軍伝習所二期生(榎本武揚同期生)、幕府軍艦操練所頭取、勝海舟、福沢諭吉らと共に咸臨丸で訪米。日本の造船の父といわれる。岩倉使節団理事官。
ひだためよし
1812-1876
松平京家信頼流
酒井忠発 [大名]
《従四位下・左衛門尉 侍従》
出羽国庄内藩の第九代藩主。酒井佐衛門尉家十五代当主。
天保十年(1839)二月、現在の東京都墨田区錦糸町付近で釣り上げられた鮒の魚拓「錦糸堀の鮒」が日本最古の魚拓とされ、忠発が釣り上げたものとされている。
さかいただあき
1810-1864
松平京家頼信流
堀田正睦 [大名・老中首座]
《従四位下・侍従 贈従三位》
下総国佐倉藩五代藩主。
南関東の学都と呼ばれた佐倉藩の藩主。学問に関する特徴は、知識のコレクションではなく体系的な学問を志向した結果として、幕末と明治に有為の人材を育成した点にある。
ほったまさよし
家紋
三条紋
定紋
![]() 三条蝶
三条蝶
替紋
![]() 十二葉菊
十二葉菊
皇紋
定紋
![]() 皇蝶
皇蝶
替紋
![]() 皇雨龍
皇雨龍
徳紋
定紋
![]() 花器章
花器章
替紋
![]() 橋三つ引き
橋三つ引き
![]() 冥神流
冥神流
「冥心」
神を宿し心にその目は開かれる。
伝承者
三条亨輝
第一代冥神流伝承者
皇霞京 冥月
すめらぎかきょう
松田宗家伝承
伝承者
三条亨輝
第二十九代松田宗家伝承者
![]() 皇霞京 冥月
皇霞京 冥月
三条輝政
第二十八代松田宗家伝承者
![]() 松田守
松田守
三条輝治
第二十七代松田宗家伝承者
![]() 芦田幸太郎
芦田幸太郎
三条輝成
第二十六代松田宗家伝承者
![]() 吉野作造 古川学人
吉野作造 古川学人
三条輝耡
第二十五代松田宗家伝承者
![]() 上野英三郎 農学博士
上野英三郎 農学博士
三条輝照
第二十四代松田宗家伝承者
![]() 大河内輝声 源桂閣
大河内輝声 源桂閣
三条輝聴
第二十三代松田宗家伝承者
![]() 福澤範 諭吉
福澤範 諭吉
三条正敬
第二十二代松田宗家伝承者
![]() 大塩後素 中斎
大塩後素 中斎
三条正路
第二十一代松田宗家伝承者
![]() 華岡震 青洲
華岡震 青洲
三条正升
第二十代松田宗家伝承者
![]() 伊能忠敬 東河
伊能忠敬 東河
三条正温
第十九代松田宗家伝承者
![]() 平賀源内 鳩渓
平賀源内 鳩渓
三条信祝
第十八代松田宗家伝承者
![]() 久留島義太 沾数
久留島義太 沾数
三条信輝
第十七代松田宗家伝承者
![]() 新井君美 白石
新井君美 白石
三条輝綱
第十六代松田宗家伝承者
![]() 土佐光起 春可軒
土佐光起 春可軒
三条正永
第十五代松田宗家伝承者
![]() 林信勝 羅山
林信勝 羅山
松田頼通
第十四代松田宗家伝承者
![]() 結城秀康 越前宰相
結城秀康 越前宰相
松田頼勝
第十三代松田宗家伝承者
![]() 伊達政宗 独眼竜
伊達政宗 独眼竜
松田達頼
第十二代松田宗家伝承者
![]() 織田信長 建勲
織田信長 建勲
松田頼信
第十一代松田宗家伝承者
![]() 上杉輝虎 不識庵謙信
上杉輝虎 不識庵謙信
松田家頼
第十代松田宗家伝承者
![]() 武田晴信 徳栄軒信玄
武田晴信 徳栄軒信玄
松田信頼
第九代松田宗家伝承者
![]() 毛利元就 羽柴安芸宰相
毛利元就 羽柴安芸宰相
松田頼済
第八代松田宗家伝承者
![]() 北条早雲 伊勢宗瑞
北条早雲 伊勢宗瑞
松田善通
第七代松田宗家伝承者
![]() 北畠教具 権大納言
北畠教具 権大納言
松田頼仲
第六代松田宗家伝承者
![]() 斯波義敦 勘解由小路武衛
斯波義敦 勘解由小路武衛
松田頼源
第五代松田宗家伝承者
![]() 大内義弘 香積寺殿秀山仁実
大内義弘 香積寺殿秀山仁実
松田頼近
第四代松田宗家伝承者
![]() 六角氏頼 三郎
六角氏頼 三郎
松田頼貞
第三代松田宗家伝承者
![]() 仁木頼章 二郎三郎
仁木頼章 二郎三郎
松田頼直
第二代松田宗家伝承者
![]() 京極宗氏 佐渡判官
京極宗氏 佐渡判官
松田頼盛
第一代松田宗家伝承者
![]() 今川国氏 国光寺
今川国氏 国光寺
家紋相対
![]() 福澤
福澤 ![]() 吉野
吉野
![]() 伊能
伊能 ![]() 華岡
華岡
![]() 上野
上野 ![]() 松田
松田
![]() 土佐
土佐 ![]() 久留島
久留島 ![]() 大河内
大河内
![]() 林
林 ![]() 平賀
平賀
![]() 結城
結城 ![]() 新井
新井
![]() 織田
織田 ![]() 大塩
大塩 ![]() 皇
皇
![]() 上杉
上杉 ![]() 芦田
芦田
![]() 北条
北条 ![]() 毛利
毛利
![]() 大内
大内 ![]() 武田
武田
![]() 仁木
仁木 ![]() 斯波
斯波 ![]() 伊達
伊達
![]() 京極
京極 ![]() 六角
六角
![]() 今川
今川 ![]() 北畠
北畠